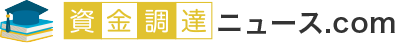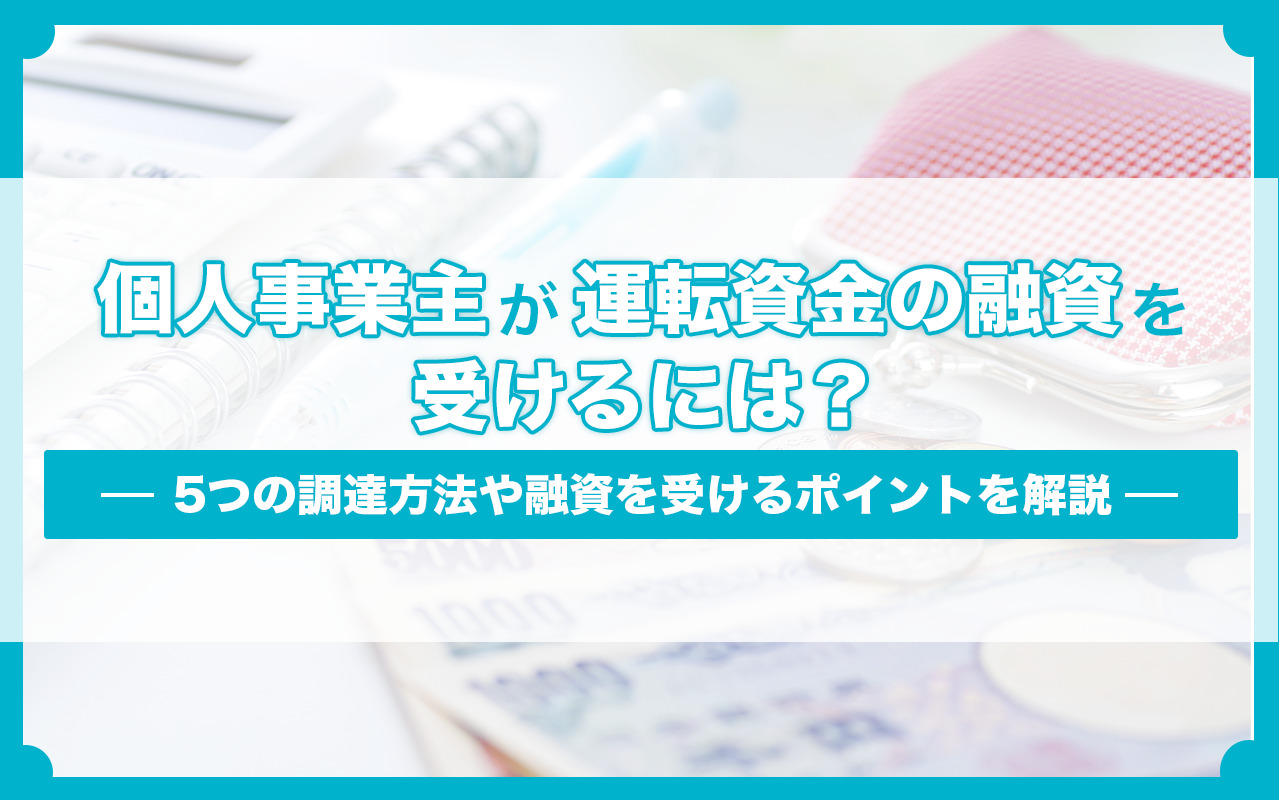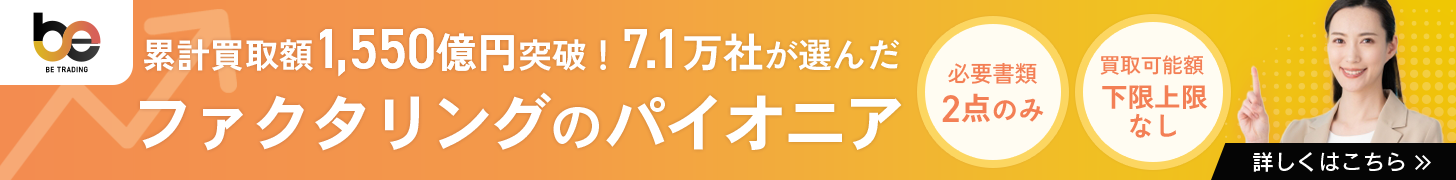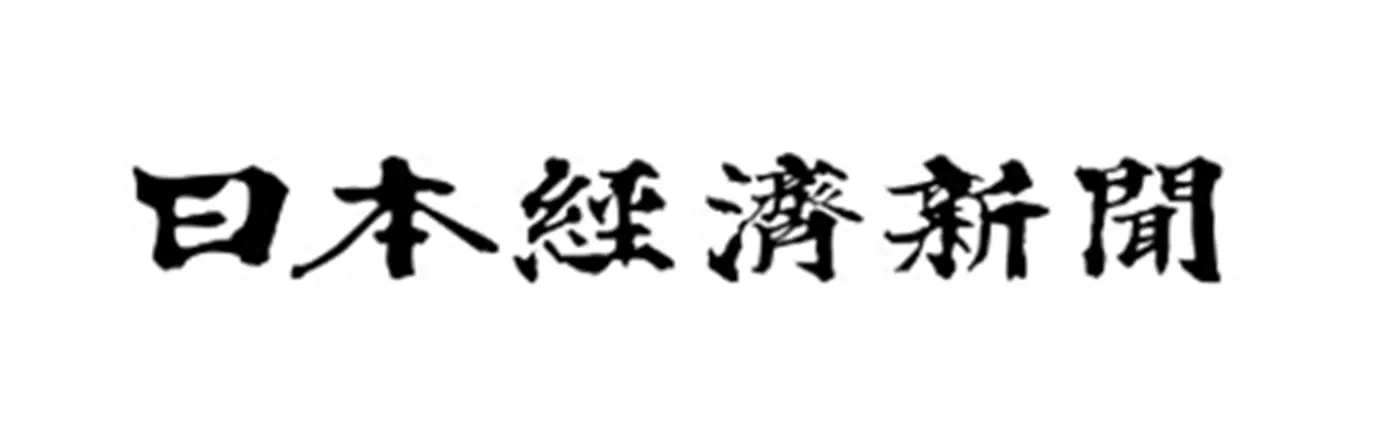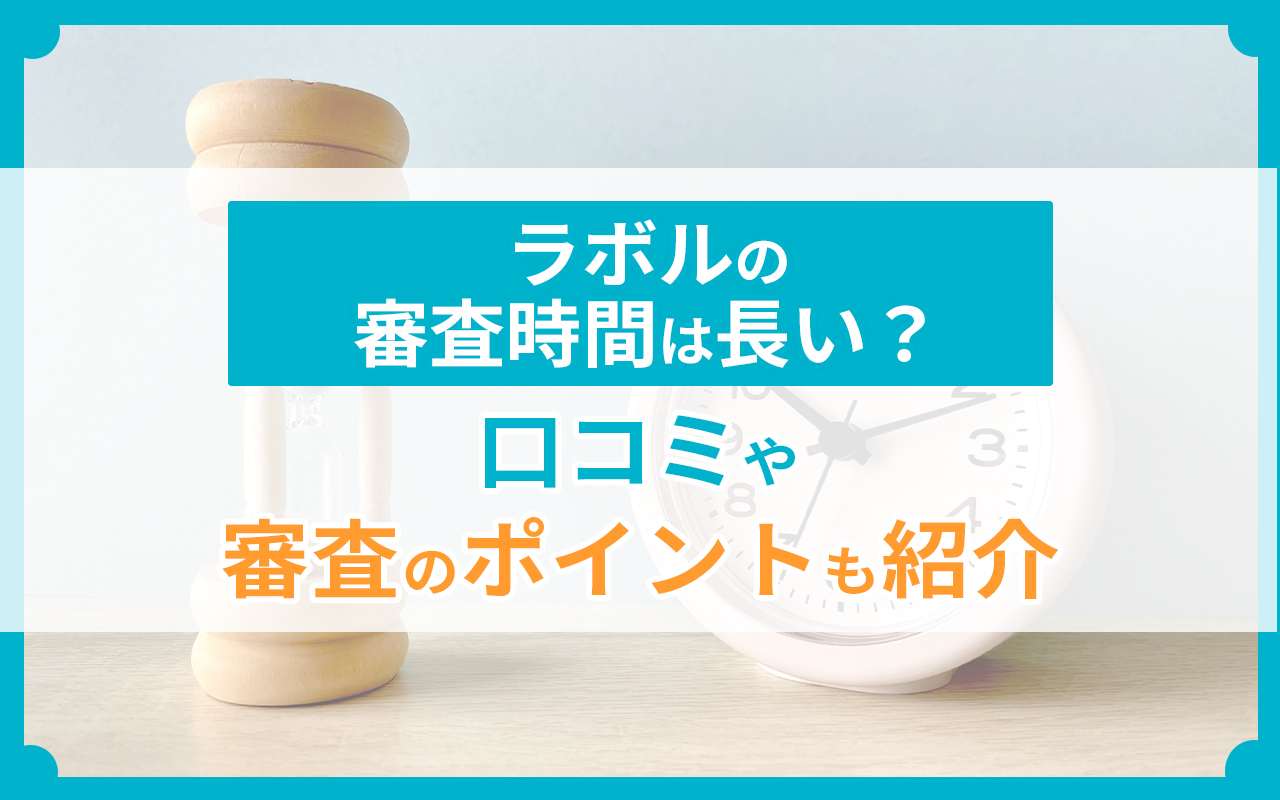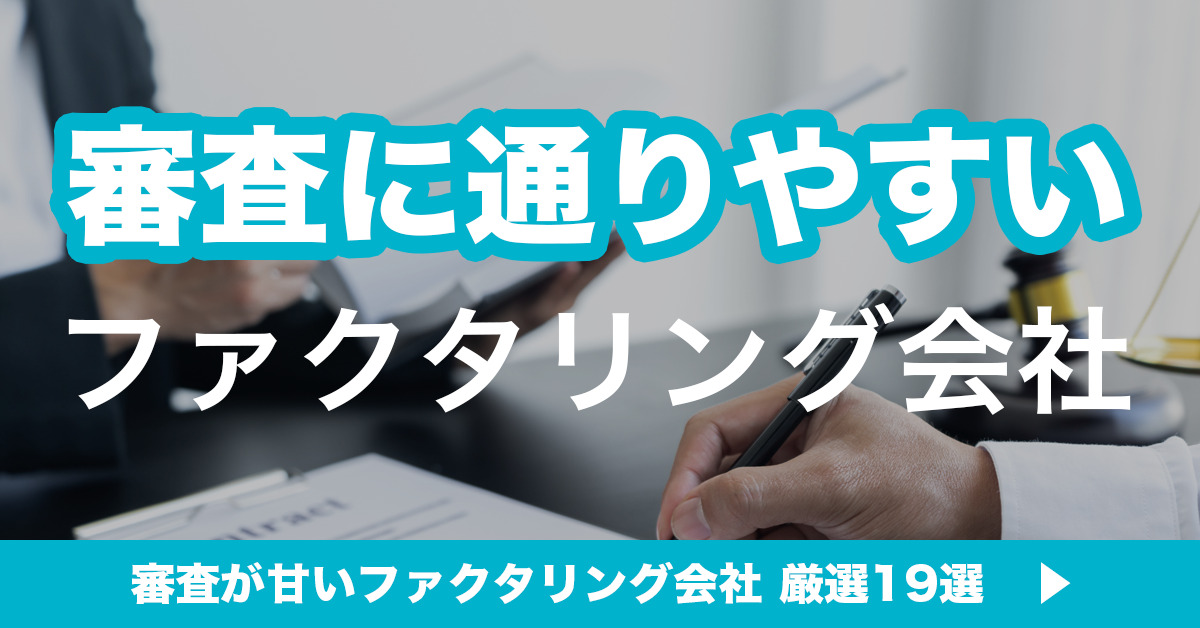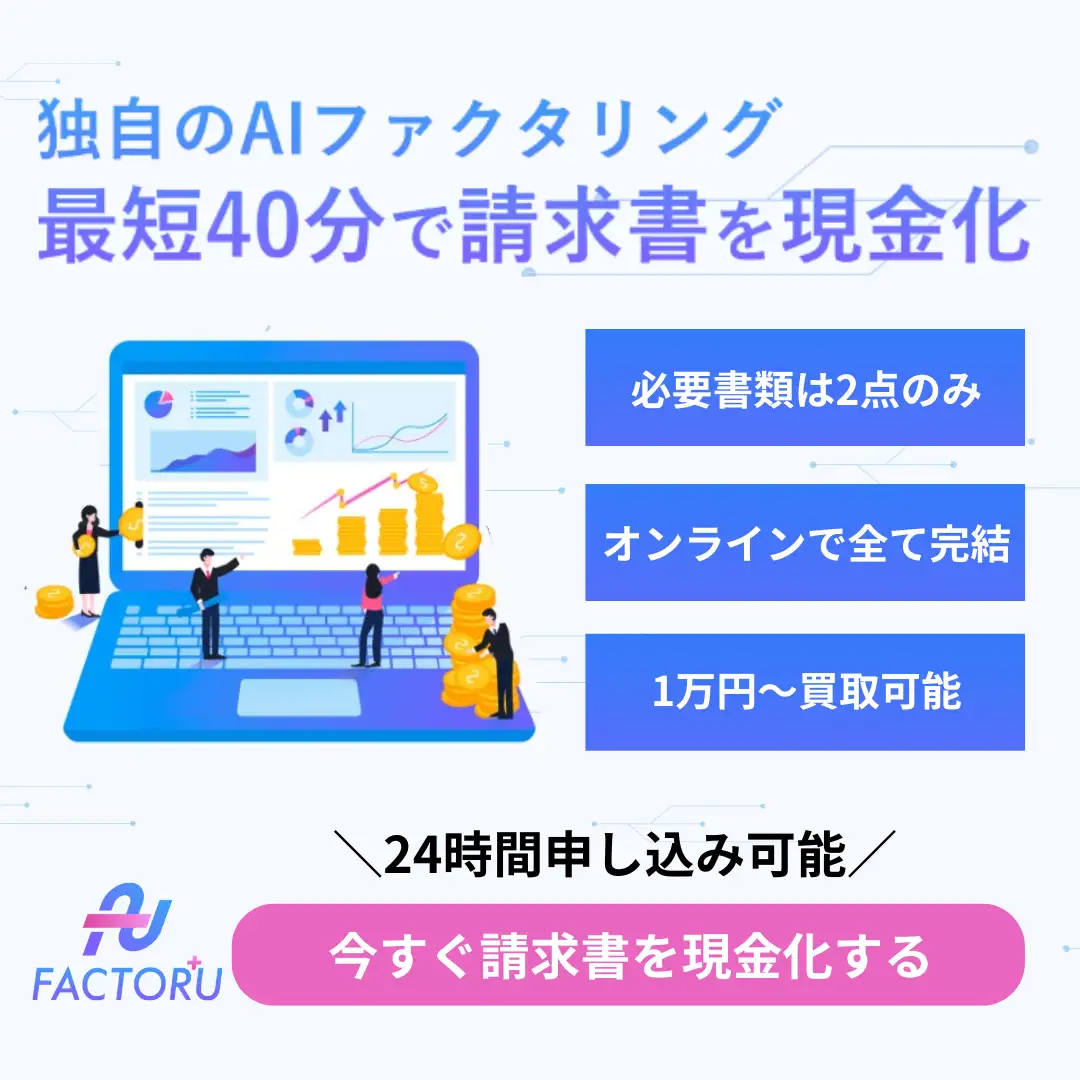そもそも運転資金とは
運転資金とは、事業の運営に必要な費用を賄うための資金のことで、いわゆるランニングコストです。
事務所の賃料や水道光熱費、材料の仕入れにかかる経費などがこれにあたります。
厳密には以下4種類の運転資金が存在しますが、一般的に“運転資金”といえば経常運転資金を指します。
【運転資金の種類】
|
特徴 |
用途例 |
| 経常運転資金 |
事業の運営で通常必要な資金 |
・賃料
・人件費
・仕入れ
|
| 増加運転資金 |
事業の拡大時に必要な資金 |
・追加の人件費や仕入れ |
| 減少運転資金 |
事業の縮小時に必要な資金 |
・店舗の閉鎖費用 |
| 季節性運転資金 |
特定の時期にのみ必要な資金 |
・社員への賞与
・季節商品の仕入れ
|
なお運転資金の用途としては、毎月必ず発生する“固定費”と、売上や市場の状況により増減する“変動費”に分けられます。
費用を固定費と変動費に分けるのは、損益分岐点や削減すべきコストを把握し、適切な事業運営を行うためです。
以上を踏まえ、自らの事業にかかる費用を正確に認識したうえで、必要な運転資金の確保に努めましょう。
固定費
固定費は、売上の増減にかかわらず、毎月一定額発生する費用です。
“たとえ売上がゼロであっても発生する費用”ともいえます。
【固定費の例】
固定費は継続的に支払い続けることになるので、新しい事務所を契約する際など、固定費が増えることになる決定については、慎重にならなければなりません。
変動費
一方で変動費は、売上や生産量、販売数の増減によって変動する費用です。
固定費とは違って決まった金額ではないため、月ごとに調整することが可能です。
【変動費の例】
これらの費用を見直すことで、必要な運転資金の額を抑えられます。
仕入れ先との価格交渉や外注先の変更は、商品やサービスの質に影響するおそれがあるので、まずはペーパーレス化など、売上とは無関係の部分から取り組むとよいでしょう。
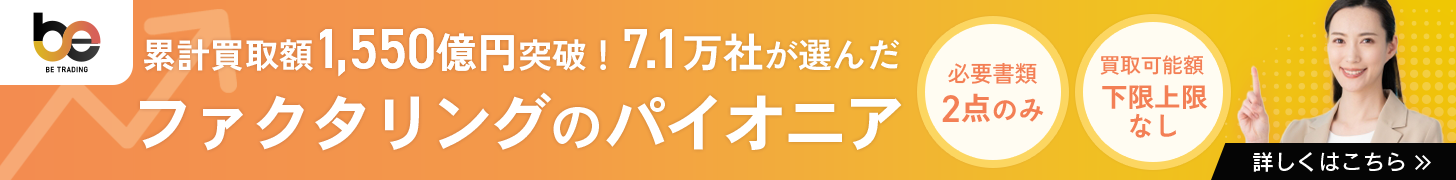
個人事業主の運転資金の調達方法
個人事業主が運転資金を調達する方法は、銀行融資だけではありません。
ここからは、個人事業主が受けられる融資の借入先をいくつか紹介します。
ご自身の状況に合わせて、適切な資金調達方法を選択してください。
日本政策金融公庫
個人事業主が運転資金を調達する際にまず検討したいのが、日本政策金融公庫をはじめとする公的融資です。
公的融資は、国や自治体から融資を受けることになるため、営利目的の銀行や消費者金融と比べて金利が抑えられています。
日本政策金融公庫が実施している融資制度のうち、個人事業主が利用できる制度は以下の通りです。
新規開業・スタートアップ支援資金
| 融資限度額 |
7,200万円(うち運転資金4,800万円)
|
|
利率(年)
|
基準利率(令和7年4月1日現在2.90%~4.00%)※一定の要件を満たす場合は特別利率
|
|
返済期間
|
設備資金:20年以内運転資金:10年以内
|
|
担保・保証人
|
応相談
|
新規開業・スタートアップ支援資金は、若者からシニアまで年齢を問わず、また、過去の廃業歴があっても審査に通過すれば資金を支援してもらえる制度です。
日本政策金融公庫が過去に取り扱っていた“新創業融資制度”の後継制度であり、そのうえ以前よりも柔軟に、無担保・無保証人で融資を受けることが可能となりました。
経営者保証免除特例制度や創業支援貸付利率特例制度など、併用できる特例制度もあるので、申請時に公式サイトを確認するとよいでしょう。
参照:日本政策金融公庫
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)
| 融資限度額 |
2,000万円
|
|
利率(年)
|
特別利率F(令和7年4月1日現在2.00%)
|
|
返済期間
|
10年以内
|
|
担保・保証人
|
無担保・無保証人
|
マル経融資(小規模事業者経営改善資金)は、商工会議所や商工会などが実施する経営指導を受けている小規模事業者の商工業者を対象とした制度です。
融資限度額は2,000万円と高額で、要件を満たしていれば、個人事業主であっても無担保・無保証人で融資を受けられます。
また、他の融資制度と比べて利率(年)が2.00%と低く、負担が抑えられている点が特徴です。
参照:マル経融資(小規模事業者経営改善資金)|日本政策金融公庫
信用保証協会の制度融資
公的融資の選択肢としては、信用保証協会が扱っている“制度融資”も挙げられます。
信用保証協会は、中小企業や小規模事業者の資金調達を支援する公的機関です。
全国各地に設置されており、融資に必要な保証業務を地域密着型で行っています。
制度融資は、信用保証協会と自治体、地域金融機関が連携して実施している融資制度で、中小企業や個人事業主に必要な事業資金を用立てることを目的としたものです。
自治体ごとに制度の内容や条件が異なるため、詳細はお近くの信用保証協会にお問い合わせください。
ビジネスローン
ビジネスローンは、その名の通り、事業資金専用のローンです。
公的融資や銀行融資と比較して、申し込みから審査、入金に至るまでのスピードが早く、原則無担保・無保証人で利用できる点がメリットです。
ビジネスローンは消費者金融やクレジットカード会社など、多くの事業者が取り扱っており、融資限度額や利率などは提供元によって異なります。
利率は公的融資や銀行融資以上に高く設定されている傾向にあるため、利用する際は慎重に検討したいところです。
カードローン
銀行や消費者金融が提供する、カードローンを利用するのも選択肢の一つです。
カードローンは使途が定められていない個人向けのキャッシングサービスで、個人事業主が運転資金の用途で利用しても問題ありません。
また、契約の限度額の範囲内であれば、何度でも自由に借り入れが可能です。
ただし、適用される金利は比較的高く、返済が長期化すると負担が大きくなる点は注意しなければなりません。
信用金庫
地域密着型の金融機関である信用金庫も、個人事業主が利用できる融資元です。
信用金庫は相互扶助による地域の繁栄を目的に、その地域で事業を行う中小企業や個人事業主に向けて融資を行っています。
株式会社である銀行とは異なり、営利目的ではない、地域社会の発展に貢献するための金融機関です。
【信用金庫と銀行の違い】
|
信用金庫 |
銀行 |
| 根拠法 |
信用金庫法 |
銀行法
|
| 増加運転資金 |
会員の出資による協同組織の非営利法人 |
株式会社組織の営利法人 |
| 会員資格(事業者の場合) |
従業員300人以下または資本金3億円以下の事業者 |
なし |
| 業務範囲 |
融資は原則として会員を対象とするが、制限つきで会員外貸出も可能 |
制限なし
|
信用金庫の場合、会員であれば大企業でなくとも比較的融資を受けやすいというメリットはありますが、融資の対象地域が限定されている点は留意しておきましょう。
運転資金の目安
必要な運転資金の額は業種や事業規模、資金繰りの状況によって異なりますが、月商の3か月分~6か月分が目安だといわれています。
たとえば、建設業や運送業は売掛金を回収するまでの期間が他の業種より長いため、多額の運転資金を要します。
一方で飲食業などは、現金で支払いを行われることもあるため、掛取引が一般的な業種と比較して、手元に確保しておく資金は比較的少なくて済むでしょう。
なお、必要な運転資金は以下の式で算出することも可能です。
たとえば、売掛金などの売上債権が500万円、棚卸資産が600万円、仕入債務が400万円だった場合、必要な運転資金は次のように求められます。
|
運転資金=500万円+600万円-400万円=700万円
|
いずれにせよ、これは必要な資金の最低限の目安であって、手元にある現金は多いに越したことはありません。
売掛金の回収が遅れたり突発的な出費が発生したりと、不測の事態が起こったときに事業を継続できるだけの余裕が必要です。
【シチュエーション別】個人事業主におすすめの運転資金の調達方法
適切な資金調達の手段は、ご自身が何を重視するかによって変わります。
それぞれのメリットとデメリットを把握したうえで、条件に合う選択肢を選びましょう。
ここからは、シチュエーション別におすすめの運転資金の調達方法を紹介します。
スピードと手軽さを重視する場合
融資までのスピードと利用の手軽さを重視する場合、カードローンがおすすめです。
カードローンは、初めて利用する場合でも申し込みから最短即日で資金調達が叶います。一度契約してしまえば、利用限度額に達しない限り、利用可能です。
利用限度額は、他社の借入状況なども踏まえたうえで、貸金業法で定められた“総量規制”の範囲内で決定されます。
ただし、年利は上限18%程度と他の資金調達方法より高い点がネックです。
高い金利に目をつぶってでも利便性を最優先したい事業者に適した調達先といえます。
年収に関係なく借り入れたい場合
消費者金融のカードローンなどは、総量規制によって「個人が借り入れられる金額は年収の3分の1まで」と定められています。
この総量規制の制限を受けない手段を望む場合は、借入金額に上限がないビジネスローンを利用するとよいでしょう。
そもそもビジネスローンは「一般的な銀行融資を受けられない、中小企業や個人事業主でも資金を調達できるように」と生まれた金融商品です。
他の資金調達方法では、年収を理由に希望の金額を調達できない事業者にとって、頼みの綱ともいえる存在です。
カードローンと同様に、年利が上限18%程度と高めに設定されている点には注意しましょう。
事業開始から間もない場合
まだ事業を立ち上げて間もない場合は、日本政策金融公庫の融資をはじめとする公的融資が最適です。
銀行融資やビジネスローンなどは、審査の際に過去の業績が求められます。
ただし、開業したばかりのタイミングでは、提示できる実績がないことから、融資を受けることは極めて難しいといえるでしょう。
その点、公的融資であれば創業時に利用できる融資制度が充実しているため、事業計画書に問題がなければ審査に通る可能性があります。
審査には数週間から1か月ほどかかるものの、選択肢が限られる状況においては、有力な手段の一つです。
強力なサポートを受けたい場合
融資の審査にあたって手厚いサポートを受けたければ、信用金庫から融資を受けることを視野に入れてください。
先述の通り、信用金庫は利益を追求しない、地域の繁栄に寄与するための金融機関です。
その地域で事業を営んでいれば、信用力が高くない個人事業主であっても融資を前向きに検討してもらえるはずです。
信用金庫によっては個人事業主専用の窓口が設けられていることがあり、事業計画書の作成をサポートしてもらえます。
このように地域密着型の金融機関としての利点がある反面、対応できる地域が制限されているため、事業拠点を移した場合は利用できなくなります。
他の地域への事業拡大を予定している場合は、信用金庫以外のパートナーを探したほうがよいでしょう。
金利を抑えたい場合
金利を抑えることを第一に考えたい場合は、カードローンやビジネスローンと比較し、低金利での借り入れが可能な銀行融資が適しています。
審査に時間を要する点に問題がなければ、最初に申し込んでみましょう。
懸念としては、やはり融資審査の難易度が高い点です。
事業者の信用力が厳しくチェックされるため、創業から間もない場合や、財務状況が思わしくない場合は、審査に落ちてしまうかもしれません。
運転資金を確実に確保したいのであれば、他の手段もあわせて検討したいところです。
個人事業主が運転資金の融資を受ける際のポイント
事業の成長や安定した運営には、適切なタイミングで運転資金を調達することが欠かせません。
ここからは、資金調達の際に注意すべきポイントを整理し、事業を安定させるために意識したいことを解説します。
ポイント①必要な額だけ借りる
多くの金融機関では、個人事業主向けにある程度の融資限度額が設定されています。
「手元のキャッシュが不足してしまう」という不安から、多くの資金を調達したいと考えるかもしれませんが、だからといって限度額上限まで借り入れる必要はありません。
事業の現状や将来的な収支の見通しに基づき、実際に必要となる資金額を正確に算出したうえで利用してください。
必要以上に借り入れると、金利や返済総額が増加し、キャッシュフローを圧迫するおそれがあります。
無理のない範囲で最低限の資金調達にとどめることが、事業運営の健全性を保つうえで非常に大切です。
ポイント②実現可能な返済計画を立てる
返済計画の策定は、融資を受ける際に重要なステップの一つです。
個人事業主は収入が安定しないことが多いため、毎月の返済可能額を現実的に見積もる必要があります。
「これくらいの金額なら毎月返済できるだろう」と楽観視せず、事業の閑散期でも無理なく返済を続けられるスケジュールを組むことが求められます。
融資担当者に提出する事業計画書には、返済計画の根拠となる具体的な数字や見通しを明記し、信頼性の高いプランを示すことが、審査に通過する鍵です。
ポイント③書類に不備がないことを確認する
融資の申し込み時に提出する決算書や事業計画書などは、金融機関が事業者の信用力や運営状況を判断するための資料です。
【融資の申し込みに必要な書類の例】
- 決算書
- 試算表
- 資金繰り表
- 事業計画書
- 納税証明書
- 本人確認書類
一つでも不備や誤記があれば、審査に悪影響を及ぼす可能性があります。
書類の記入漏れや内容の矛盾、事実と異なる記述がないように何度も見直し、正確な情報を反映させましょう。
事前に、専門家や第三者に確認を依頼するのも有効な手段といえます。
ポイント④資金の使途を明確にする
金融機関の融資を受ける際は、調達した資金の使い道を明確に示しましょう。
資金使途が不透明な場合、審査担当者に目的にそぐわない支出や無駄な費用が発生するリスクを指摘されてしまいます。
申し込み時には、運転資金をどのように活用するのかを示した、具体的な事業計画書を作成しなければなりません。
設備投資や仕入れ、広告宣伝費など、資金使途の内訳を細かく整理し、関連する資料や見積もりを添付することで、説得力のある事業計画書が完成します。
ポイント⑤金利や手数料を確認する
融資を受けたあとは、借り入れた元金の返済だけでなく、金利やその他の手数料の支払いを含めて、事業の資金繰りを考えなければなりません。
特に借入金額や返済期間が長期にわたる場合、総返済額は当初想定していた以上に膨らんでしまいがちです。
金利の利率はもちろん、固定金利か変動金利かといった選択肢も含め、各金融機関が提示する条件を十分に比較検討してください。
予想外の負担が発生しないかを契約前に確認することが、安心して運転資金を活用する基本となります。
個人事業主が利用できる融資以外の方法
ここまででお伝えしたポイントを踏まえたうえで、どうしても融資の審査に通らなかったのであれば他の方法を検討する他ありません。
ここからは、補助金・助成金やファクタリングといった、運転資金を得るために利用できる融資以外の方法を解説します。
補助金・助成金
補助金や助成金は、国や地方自治体、商工会議所などが提供している支援制度で、採択されれば原則として返済は不要の資金調達方法です。
創業支援や販路拡大、業務効率化など、用途に応じた多様な制度が用意されています。
たとえば“小規模事業者持続化補助金”は、設備導入費や広告費の一部を補助してくれる制度で、多くの個人事業主が活用しています。
補助金や助成金で受け取れる金額は、一般的に数十万円~数百万円程度に過ぎませんが、資金繰りの負担軽減効果は十分です。
ただし申請には複数の書類が必要で、審査に時間がかかるため、スケジュールに余裕を持たせて準備を進めましょう。
制度によっては定員や応募期間に制限が設けられているので、常に最新情報のチェックが欠かせません。
クラウドファンディング
クラウドファンディングは、インターネットを通じて不特定多数の人々から資金を集める仕組みです。
新商品の開発やイベントの開催といった明確な目的があるプロジェクトに適しており、近年では個人事業主の間でも活用が広がっています。
クラウドファンディングにはいくつかの形式が存在しますが、“購入型”や“寄付型”であれば、法人格を持たなくとも利用しやすいでしょう。
【個人事業主が利用しやすいクラウドファンディングの形式】
| 形式 |
概要 |
| 購入型 |
支援者からお金を受け取り、リターンとして商品やサービスを提供する |
| 寄付型 |
支援者から寄付というかたちでお金を受け取る |
| 株式投資型 |
支援者からお金を受け取り、株式会社が未公開株を提供する |
| ファンド型 |
支援者からお金を受け取り、事業の売上に応じてリターンを提供する |
プロジェクトが注目されれば、事業の認知拡大やファンの獲得にもつながる点が魅力ですが、目標金額に達しない場合、集まった支援金は原則返金しなければなりません。
資金を想定通りに調達できない可能性があるほか、リターンの手数料や発送費などの諸費用も事前に計算したうえで、プロジェクトを設計してください。
資産や設備の売却
事業に使っていない資産や使い道の少ない設備があれば、それらを売却することで資金を調達する方法もあります。
業務用の機械や車両、不動産などを手放して、運転資金を一時的に確保しましょう。
資産の売却は資金調達にとどまらず、業務のスリム化にもつながります。
不要な設備の維持にかかるコストやスペースが削減され、結果として経営効率の向上が期待できます。
ただし、購入時と比較して売却対象の価格が著しく下がっている場合や、売却に時間を要する場合があるため、事前の市場リサーチが欠かせません。
また、売却後に再度同じ設備が必要になるケースも考えられるので、少し先のことも想定しながら慎重に判断してください。
リースバック
リースバックは、自宅や事務所など、ご自身が保有する不動産を一度売却し、その後リース契約を結んで引き続き使用する方法です。
不動産を売却してまとまった資金を得たうえで、引き続き日常業務には支障なく使用できる点が魅力です。
その一方で、売却後はリース料の支払いが発生するため、長期的には割高になる可能性があります。
導入を検討する際は、契約条件や支払総額をよく確認し、許容できる範囲で利用することを心がけましょう。
ファクタリング
ファクタリングは、事業者が保有する売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらうことで、本来の支払期日より早く現金化できるサービスです。
ファクタリングには利用者とファクタリング会社の2者間で契約を行う形態と、そこに売掛先も交えた3者間で契約を行う形態の2種類が存在し、それぞれ取引の仕組みや手数料率の相場が異なります。
|
2者間ファクタリング |
3者間ファクタリング |
| 手数料率 |
8%~18% |
2%~9% |
| 売掛先の承諾 |
不要 |
必要 |
| 債権譲渡登記 |
サービスによっては必要 |
不要 |
ファクタリングの具体的なメリットは、次項で詳しく解説します。
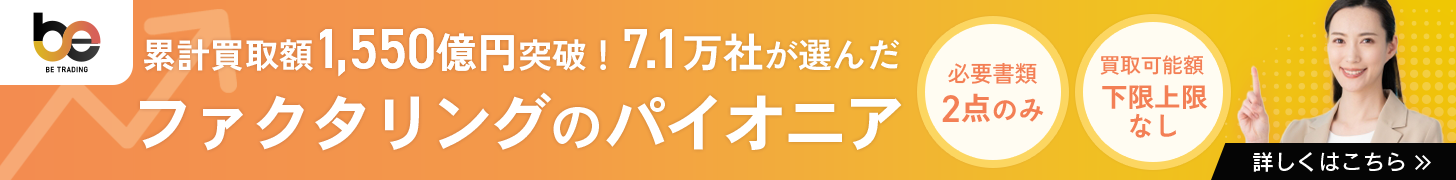
個人事業主がファクタリングを利用するメリット
ここでは、ファクタリングを使用する代表的な3つのメリットをお伝えします。
メリット①最短即日で入金される
ファクタリングの最大の特徴は、資金をスピーディーに調達できる点です。
売掛金の本来の支払期日よりも早期に現金化できるというのはもちろん、ファクタリング会社によっては、申し込みから最短即日での入金も叶います。
銀行融資の場合は、申し込みから入金までに1か月程度かかることも珍しくないため、ファクタリングによる資金調達の早さがおわかりいただけるはずです。
急な支払いへの対応や、資金繰りへの早急な改善など、時間に余裕がないときでも売掛金さえあれば現金にすぐに変えられる点は大きな魅力です。
メリット②担保や保証人は必要ない
個人事業主の場合、担保にできる資産を持っていなかったり、保証人を立てるのが難しかったりすることも珍しくありません。
しかし、ファクタリングであれば、そのようなハードルの高さを気にすることなく、資金の調達が可能です。
ファクタリングは売掛金の売買契約であり、融資とは異なります。
そのため、通常の融資で求められる不動産などの担保や保証人は原則不要です。
ただし、ファクタリング会社によっては、保証人や担保が必要となる場合もあるので、申し込み時に確認しておくと安心です。
メリット③税金の滞納があっても利用できる可能性がある
ファクタリングでは、利用者が税金を滞納していることを理由に利用を断られるケースがほとんどありません。
ここまでで紹介した多くの資金調達方法では、税金や社会保険料に滞納があると、審査に通過することが難しくなります。
特に銀行融資においては「返済能力がない」と判断される可能性が高いでしょう。
しかしファクタリングの審査では、利用者の信用情報は重視されない傾向にあるため、税金や社会保険料を多少滞納していた場合でも利用できる可能性は大いにあります。
重視されるのは支払義務がある売掛先の信用力であり、取引を行っている企業の経営状況が安定しているかどうかが、重要なポイントといえます。
税金などの滞納を理由に融資を断られた際は、ファクタリングが有力な選択肢となるでしょう。
個人事業主がファクタリングを利用する際の注意点
続いて、個人事業主がファクタリングを利用する際に注意したいポイントを紹介します。
注意点①売掛先の信用力が審査される
繰り返しになりますが、ファクタリングの審査では、資金を必要とする個人事業主自身ではなく、売掛先の信用力が重視される傾向にあります。
このため、売掛先の信用力が不十分、または取引実績が乏しい場合は、審査に通らない可能性があります。
たとえば、以下のような状況では注意が必要です。
【ファクタリングの審査に通らない可能性があるケース】
- 売掛先が実在しているかが不明確な場合
- 売掛先の業績が不安定な場合
- 売掛金の支払期日までの期間が長い場合
なお、売掛金に債権譲渡禁止特約がついている場合、トラブルを避けるために買い取りを拒否するファクタリング会社も存在します。
注意点②手数料が発生する
ファクタリングを利用する際は、ファクタリング会社に支払う手数料が発生します。
手数料は、ファクタリング会社や取引の形態、売掛金の内容などによって異なります。
たとえば、売掛先の承諾を必要としない2者間ファクタリングは、利便性が高い反面、ファクタリング会社にとっては売掛金の存在を売掛先に直接確認できないことから未回収のリスクが高いため、一般的に手数料が3者間ファクタリングと比較して割高です。
このように金融機関の融資で金利が発生するように、ファクタリングには手数料がかかります。
手数料の相場やファクタリング業界の動向をある程度把握しておくことで、不当な条件で契約してしまうリスクを軽減できます。
個人事業主が運転資金を調達する手段は様々
本記事では、個人事業主が運転資金を調達する方法を解説しました。
個人事業主は法人と比べて信用力が低く、融資の審査に通るのは難しいのは事実です。
ただし、申し込み前にいくつかのコツを押さえておけば、融資を受けられる可能性を高めることが可能です。
それでも審査に落ちてしまう場合や、審査結果が出るのを待っている余裕がない場合は、融資以外の手段も検討しましょう。
ファクタリングであれば、最短即日で入金されるうえに、税金や社会保険料を滞納していても利用できます。
資金調達ニュース.comでは、個人事業主が利用できる優良なファクタリング会社を多数紹介しています。
今すぐに資金を調達したい事業者様は、ぜひ参考にしてください。
OA機器販売会社にて財務・経理・人事などの要職を歴任し、豊富な実務経験を有する。
2021年には、日本中小企業金融サポート機構の代表理事に就任し中小企業の金融に関わる専門家として、中小企業の経営者や個人事業主が抱える資金面・経営面の課題解決に尽力。
「日本の中小企業の経営者・個人事業主の皆様が抱える資金面や経営面の課題を解決し、日本を元気で豊かにしたい」という信念のもと、さまざまな金融に関する悩みに対し、適切なサポートを提供している。
個人事業主が運転資金の融資を受ける際のよくある質問
Q.個人事業主でも通りやすい融資はなんですか?
ビジネスローンなら、公的融資や銀行融資と比較して審査が柔軟といえます。
また、原則無担保・無保証人で利用できる点もメリットです。
Q.個人事業主の運転資金の使途に生活費を含むことは可能ですか?
多くの融資では資金使途が指定されているため、生活費に充てることはできません。
違反すると融資元からの信用を失い、追加の融資が受けられなくなります。
Q.融資に申し込むのが初めてなのですが、どの方法がおすすめですか?
手厚いサポートを受けられる信用金庫の融資がおすすめです。
その地域で事業を営んでいる場合は、資金調達の相談に親身に乗ってもらえます。
Q.ブラックリストに登録されているのですが、融資を受けることは可能ですか?
ブラックリストに登録されている場合、金融機関の審査に通るのは困難です。
ファクタリングや他の手段で資金を調達しましょう。