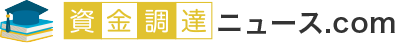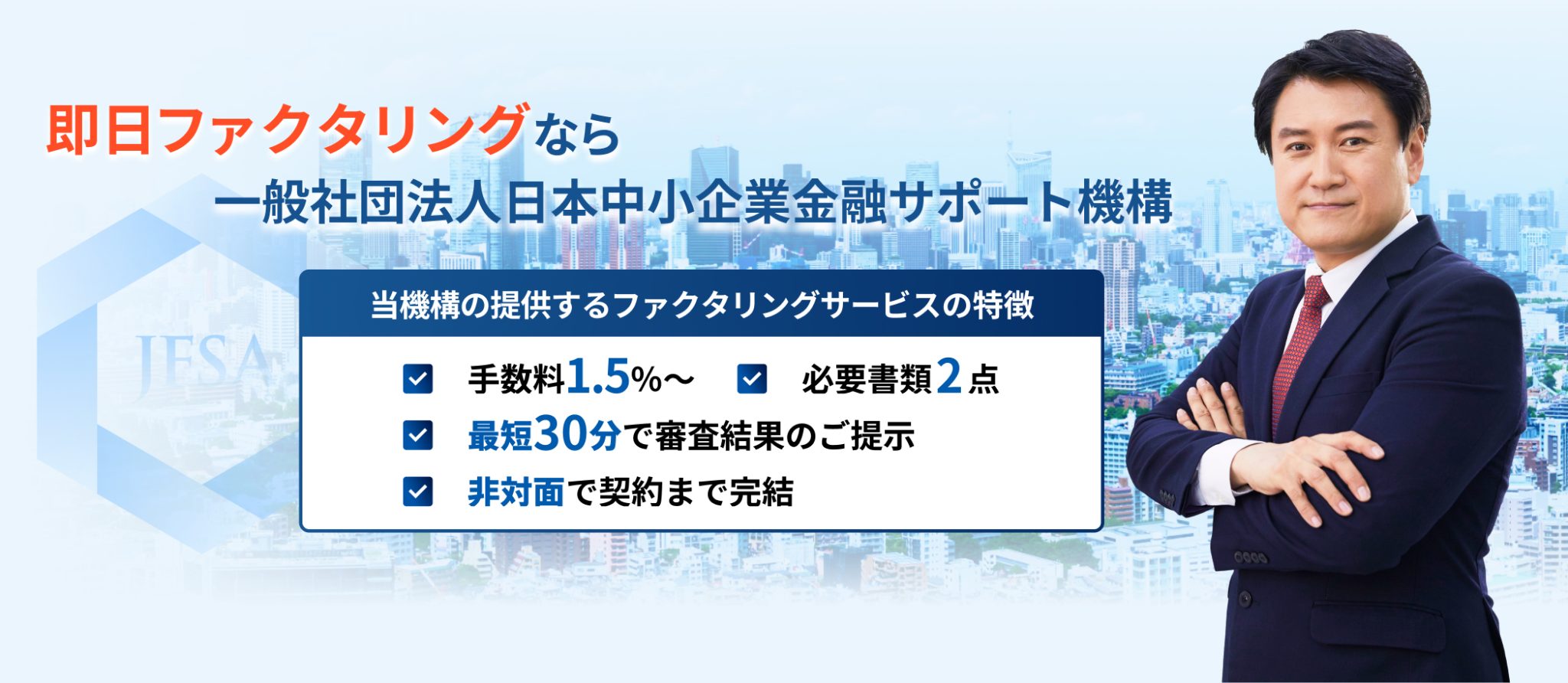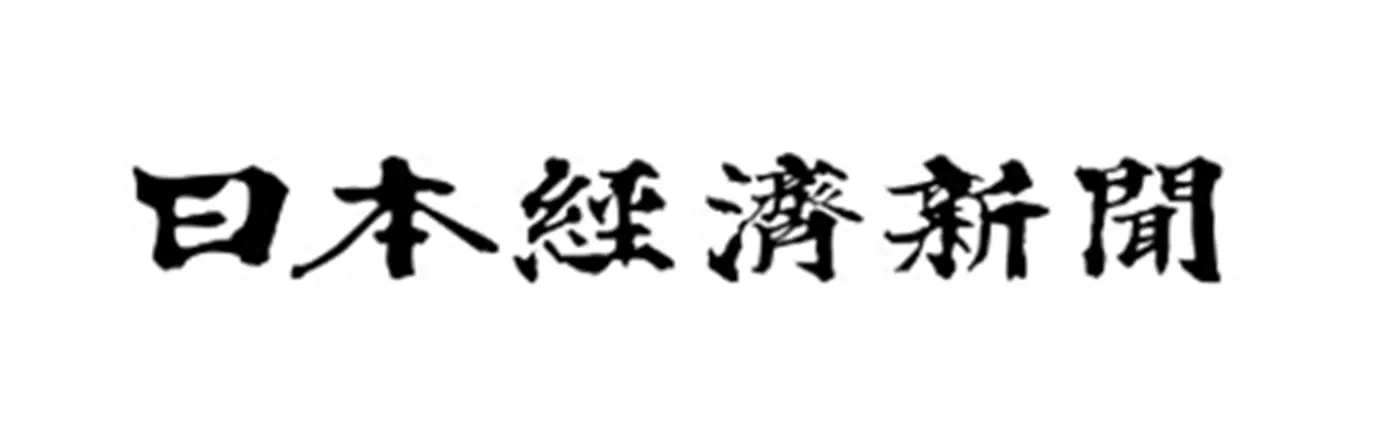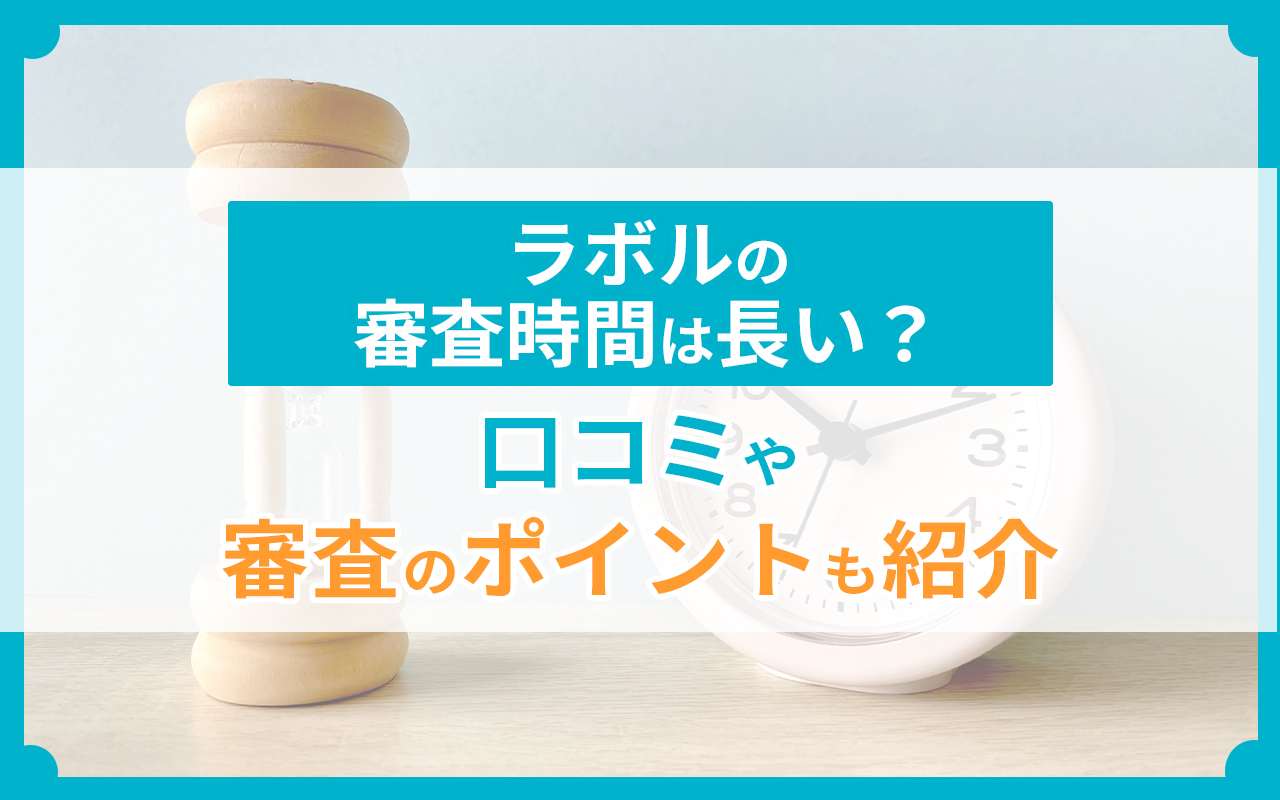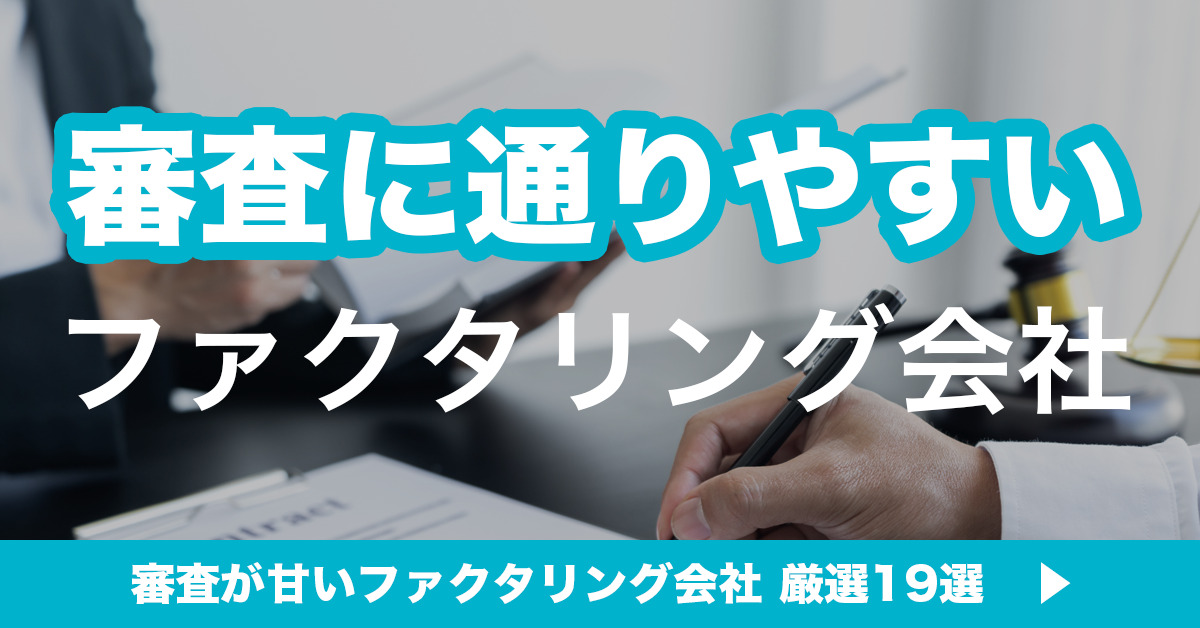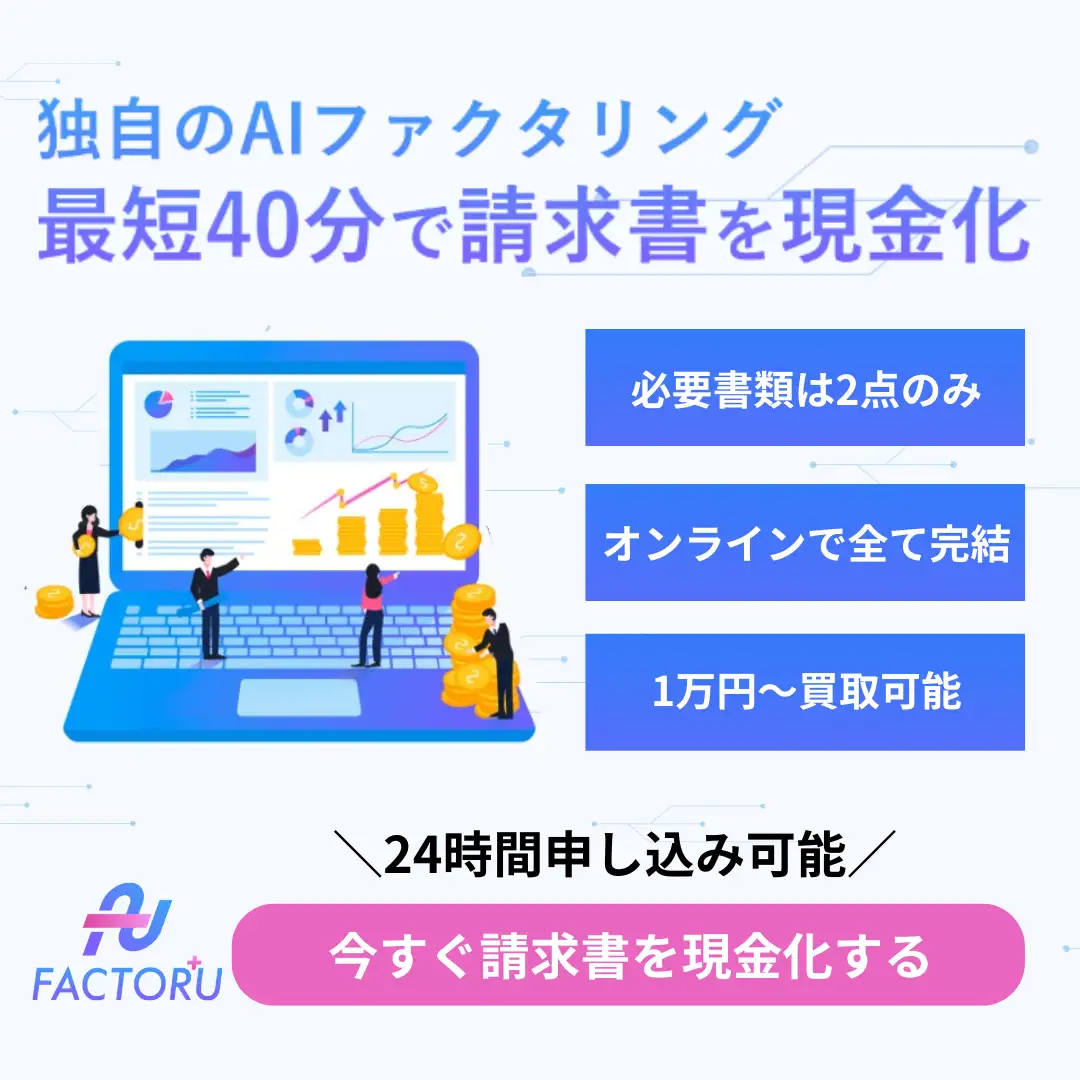起業後に運転資金不足に陥り、どうしてもすぐに借りなければならないという状況になってしまうことは、十分考えられます。
ただ、そのような状況で融資を申し込むのと、起業前にあらかじめ運転資金を多めに借りておくのでは、借りやすさに大きな違いがあります。
お金を貸す側からすれば、資金繰りに困っている会社に融資するのはリスクが高いと考えるのが普通だからです。
したがって起業する際には、負債は増えますが多めに運転資金を借りておいたほうがよいでしょう。
ただし借りすぎると返済負担が重くなってしまうので、事前に返済シミュレーションを行ったうえで、借りる金額を決めるのが賢明です。
返済開始は遅く返済期間は長く設定する
融資を受ける際、ある程度の返済プランを自分で決められる状況であれば、返済開始時期は遅く、返済期間はできるだけ長く設定しましょう。
起業時や起業後には、予期していないさまざまなトラブルに見舞われる可能性があります。
そして、そのトラブルによって想定外の出費がかさむと運転資金に余裕がなくなり、返済が厳しくなっていきます。
そのような資金繰りの悪化を避けるために、あらかじめ返済する期間を長く設定して、一度の返済にかかる負担を少なくしておくのです。
これにより、トラブルに強い会社経営が可能となります。
調達できるまでの期間を確認する
資金が調達できるまでの日程や期間は、方法によって異なります。
そのため、「いつごろ資金が入金されるか」ということは、事前に金融機関や自治体などに確認しておいたほうがよいでしょう。
確認したタイミングまでに自己資金が尽きることのないように予定を組んで調整することで、安心して事業経営を行うことができます。
なお、金融機関や自治体と面談をする際に融資希望日を伝えておくことで、その日に間に合うように考慮してくれる場合もあります。
頼れるパートナーを見つける
金融機関の担当者の中には、起業後の資金計画などについて親身になってアドバイスしてくれる人もいます。
どこの金融機関から融資を受けようか悩んでいる場合は、担当者の姿勢を判断基準にするのもひとつの方法と言えるでしょう。
また、融資の申し込みや起業自体の手続きを一人で行うのは、なかなか骨が折れるものです。
そういった際にきめ細やかに支援をしてくれる税理士や司法書士の方を見つけておくことで、今後も大きな力となるでしょう。
使用目的を明確にする
運転資金の使い道を、あらかじめ明確にしておくことも大切です。
金融機関では、融資するかどうかを決める際に、資金の使用目的を重要な判断基準の一つとしています。
そのため、事業拡大に伴う仕入れ費用や突発的な出費に対応するための費用といったように融資の目的を具体的にすることで、金融機関からの信頼を得やすくなるのです。
また、使用目的以外で融資金を使ってしまうと資金使途違反に抵触してしまうため、この点からも使用目的は事前に整理しておきたいところです。
現実的な計画を立てる
金融機関から融資を受けるためには、根拠に基づいた現実的な事業計画書を作成することが求められます。
融資を受けたお金を全額返済できる見込みが明確になっていない事業計画書では、金融機関の審査に通りません。
事業計画書に矛盾点や希望的観測によるデータが盛り込まれていると、「お金を貸すべきでない」と判断されてしまいます。
したがって、金融機関から運転資金の融資を受ける際には、過去の経営状況や数値に基づいた収支予測などを落とし込み、現実的で説得力のある事業計画書を提出しましょう。
必要書類をきちんと準備する
金融機関から運転資金の融資を受けるためには、本人確認書類や収入証明書など金融機関指定の書類の準備を怠らないようにしなければなりません。
もしこれらの書類に不備があった場合には、差し戻され、修正したあとに再提出することが求められます。
これには時間や労力がかかるうえに、経営能力を疑われて審査に悪影響を及ぼす可能性もあります。
融資を申し込む前には必要書類が揃っており、かつ内容に誤りがないことを確認してから提出するように心がけたいところです。
自己資金を多めに用意しておく
運転資金の融資を受ける際には、できる限り多くの自己資金を準備しておくことをおすすめします。
融資の審査基準として、自己資金の金額が明確に設けられているわけではないものの、貸倒れリスクを防ぐために確認される部分です。
自己資金が少ないと、万が一返済が厳しくなったときに対処できないと判断されてしまう可能性があります。
自己資金を多めに用意しておくことで、審査を通過できる可能性が高まります。

運転資金を融資以外で調達する方法
運転資金を調達する方法は、融資だけではありません。 次のような選択肢もあります。
【運転資金を融資以外で調達する方法】
- ファクタリング
- 補助金・助成金制度
- クラウドファンディング
これらの利用も検討し、十分な運転資金を確保して事業に臨みたいところです。 以下では、それぞれの概要を紹介します。
ファクタリング
「売掛金はあるものの入金期日まで待てない」というケースにおすすめの資金調達方法が、ファクタリングです。
ファクタリングとは、ファクタリング会社に売掛金を買い取ってもらい、本来の入金期日よりも前に現金化するサービスです。
一定の手数料はかかりますが、サービスによっては最短即日で入金してくれるものもあります。
また、ファクタリングは売掛債権(売掛金)を譲受(売買)する債権譲渡契約のため、返済という概念が存在しません。
さらにファクタリングにも審査があるものの、金融機関からの融資と比べて審査が柔軟な点もファクタリングを利用するメリットです。
ファクタリングの審査では、ファクタリング会社が売掛金の未回収になるリスクを避けるために、売掛先の信用力を重視します。
つまり、事業者の信用力はあまり重視されない傾向にあるため、実績が少ない、あるいは資金繰りが芳しくない事業者の方でも、資金を調達できる可能性があります。
補助金・助成金制度
運転資金を確保する手段として、補助金・助成金制度を活用することも一つの手です。
国や自治体では、事業拡大を目指す事業者、あるいは社会情勢の変化や物価高の影響を受けた事業者などを支援するために、様々な補助金・助成金の制度を設けています。
補助金や助成金には、事業の拡大や新規事業の立ち上げを支援する“事業再構築補助金”や従業員のスキル向上やキャリア形成を支援する“人材開発支援助成金”などがあります。
こうした補助金・助成金は、基本的に返済する必要がないため、運転資金を用意する際に、ぜひ検討したい制度です。
ただし、これらの制度は申請してから入金を受けるまでに長い期間がかかるため、急な資金難での活用には向いていません。
補助金・助成金制度で運転資金を調達する際は、公式サイトにて、申請から入金までの期間や応募条件をきちんと確認したうえで利用しましょう。
参照元: 株式会社パソナ「事業再構築補助金」
厚生労働省「人材開発支援助成金」
クラウドファンディング
融資以外の方法で運転資金を調達することをお考えであれば、クラウドファンディングも候補の一つになります。
クラウドファンディングとは、資金的な支援をインターネット上で募り、不特定多数の人から少額ずつ資金を調達する方法のことです。
実績がなくても挑戦できるうえに、事業の魅力や将来性のほか、社会貢献性などを説明し、共感を得ることができれば多額の資金を調達できる可能性があります。
デメリットとしては、資金調達までに2~3か月程度と長い期間がかかってしまうことが挙げられます。
またプロジェクトに共感を得られず資金調達を実現できない場合もあり、これまでの活動が無駄になってしまう可能性も否めません。
運転資金を調達する際の注意点
ここまでご紹介した資金調達方法を利用するにしても、気をつけなければならない点がいくつかあります。
以下でその注意点を確認し、安心して資金調達を行えるように備えましょう。
資金調達する金額は適正か
金融機関から融資を受ける、またファクタリングを利用する場合には、運転資金として必要な金額を正確に見積もり、過剰な金額を調達しないことが大切です。
必要以上に運転資金を調達すると、返済額が増したり、余計な手数料がかかったりしてしまいます。
こうした負担が大きくなると、事業の安定した運営が難しくなるでしょう。
そのため、運転資金を調達する際は、できる限り正確なデータに基づいて必要な金額を算出し、その金額分のみを融資やファクタリングを利用して確保することをおすすめします。
金利や手数料率は適正か
金融機関から融資を受ける場合には金利が、ファクタリングを利用する場合には手数料率が適正な範囲内に設定されているかどうかの確認も重要なポイントです。
金利や手数料率は、業者ごとに異なります。もし、相場よりも高い金利や手数料率を設定している業者を選んでしまうと、その分負担が大きくなり経営を圧迫する可能性があります。
そのため、運転資金の調達にあたり業者を選定する際は、金利や手数料率が相場と比べて高くないかどうかを確認することが鉄則です。
目安として、銀行融資の場合の金利は年1%~3%で、ファクタリングの手数料率は、2者間ファクタリングで8%~18%、3者間ファクタリングで2%~9%といわれています。
これらの水準を大幅に超えない業者を選ぶことで、無駄なコストを抑えられるでしょう。
実現可能な返済計画を立てられているか
金融機関から融資を受ける際は、実現可能な返済計画を立てることが重要です。
なぜなら、返済計画をしっかりと立てずに融資を受けてしまうと、一時的に資金難を防ぐことはできても、その後の返済負担に耐えられず、経営状況を悪化させるリスクがあるためです。
そのため金融機関から融資を受ける際には、現在の収支状況を正確に把握するところから始めましょう。
それに基づいて毎月の返済可能額を算出し、どの程度の金額であれば融資を受けても問題なく返済できるかを見極めることが大切です。
運転資金を融資で確保する際は、余裕があるうちに使用目的を整理して申し込むことが大切
本記事では、運転資金の概要とともに、融資で資金調達する際のポイントを解説しました。
運転資金とは、仕入れ費用や人件費など、事業で日常的に発生する費用のために準備しておく資金のことです。
運転資金を融資で確保する際は、資金繰りが厳しくなる前に、使用目的を整理したうえで申し込むことが大切です。
なお、運転資金の調達方法としては、審査が比較的柔軟で、迅速な入金が期待できるファクタリングもあります。
こうした点に魅力を感じる事業者様は、ぜひ資金調達ニュース.comの記事をご覧ください。
資金調達ニュース.com では“審査が柔軟”“入金までのスピードが速い”など、様々なニーズに合わせたファクタリングサービスを紹介しております。
OA機器販売会社にて財務・経理・人事などの要職を歴任し、豊富な実務経験を有する。
2021年には、日本中小企業金融サポート機構の代表理事に就任し中小企業の金融に関わる専門家として、中小企業の経営者や個人事業主が抱える資金面・経営面の課題解決に尽力。
「日本の中小企業の経営者・個人事業主の皆様が抱える資金面や経営面の課題を解決し、日本を元気で豊かにしたい」という信念のもと、さまざまな金融に関する悩みに対し、適切なサポートを提供している。